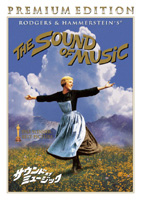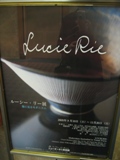2005年12月31日(土) |
一年が終わってしまうということで振り返ってみると、パリの威勢のいい爆竹で正月を迎え、2月に今のワイフと付き合いだし、GWには念願の北欧を旅して、夏はばて気味で最後は肋骨にひびまで入って大変だったけれど、なんとか秋を迎え、引越しして入籍もして一年を終えるという、なんか喜劇役者みたいな一年だった。仕事もちゃんとやったしね。僕としては上出来というところかな。 |
2005年12月30日(金) |
2005年に読んだ本のベスト |
* |
* |
2005年12月29日(木) |
|
クリント・イーストウッドの「ミリオンダラー・ベイビー」。深い味わいのある映画だった。人は希望がなければ生きていけない。逆に言えば、かすかな希望があればどんな境遇だって生きていくことはできる。しかし、苦しいエンディングだ。どうしてそれを選ばなければいけなかったのだろう。マギーをなくすことは、フランキー自身をなくすことでしかなかったのに。その苦しみの向こうに一体何があるというのか。 |
|
2005年12月28日(水) |
|
絵本に出てくるアナグマのように暖炉ならぬハロゲンストーブの前で一日過ごしてしまった(明日はどっかへ出かけよう)。 |
|
2005年12月27日(火) |
仕事納め、ということで一気に肩の力を抜いたせいか、身体が安息を求めている。節々が妙に痛む。 |
2005年12月26日(月) |
スクーリングも終了ということで気づけば明日で仕事納め。一年間でたくさんのことをやったなと思いとやりきることができなかったという思いが交錯する。でも、たとえやりきれないことがたくさんあったとしても、今年は人生の中で一度の決断しか許されない、二人乗りの自転車をこぐことに決めたのだから、素晴らしい一年という以外の形容の仕方はないだろう。 |
2005年12月25日(日) |
上司をはじめ、オフィスの人や先生にも報告。お昼の懇親会では先生のひとりがそれをしゃべったおかげで300人の拍手を受けることに・・・。ありがたい。 |
2005年12月24日(土) |
仕事から帰ってきたあと、自転車で市役所まで行って、当直室に婚姻届を出してきました。一応、イブ入籍。帰り路背中ごしふりかえると満面の笑みがあって、星空の下をどこまでも走っていけそうな、とても幸せな気分になったよ。 |
2005年12月23日(金) |
スクーリング開始。キャンパス内で待機しているのだけど、ほとんど仕事がない。昨日までが嘘のようにまったくの暇。というのもインターネット環境がない部屋なので、inputもoutputもなくなるからだ。インターネットとPCは生活を便利にしているけれど、仕事においては情報処理能力が格段と求められるようになったわけで、頭の使い方も昔と比べるとまったく変わってしまったにちがいない。もはや自分にとってはネットとPCのない頭の使い方は考えられないし、実際のところ何もない部屋に座っていても何のアイディアも湧いてこない。毎年この時期は頭がピーマンのように空になってしまう。脳が休まったところで年末休みということだから、ちょうどいいのかもしれないけれど。 |
2005年12月22日(木) |
後輩とジョーク言い合いながらずっと仕事してて楽しいのだけど、ひとりで旅に出てどこかの川のほとりでぼんやりと物思いに耽りたいような心もちもする。 |
2005年12月21日(水) |
「こころ」を読みきった。先生はKを裏切りながら、最後までひれ伏して許しを請うこともできず、その罪を背負って生きていかなければならない。そしてこの罪の意識は果てなく深い。妻の生が自分とともにあるにも関わらず、罪の意識に苛まれて自分に生の喜びを吹き込むこともできない。先生のそのような意固地さこそが、実際のところ恋愛においてKの寝首をかくような行為にうってでさせ、Kに謝ることもできなかったことに繋がっているのだろう。結局ははじめに叔父に裏切られたという思いが人に簡単に心を許さず、自分の存在に過当に重きをおくようにしてしまい、その自分がまったく叔父と同質の人間でしかなかったという失望が彼の世界への扉をすべて閉じさせてしまったのだろう。 |
2005年12月20日(火) |
係長のもってた仕事を引き継いだせいなのか、やってもやっても終わらない。午後だけでメールを15通くらい書いて、次々かかってくる電話に応対して、業者と名刺交換して・・・って感じ。夕食後、そんな一日がくやしくって「こころ」を数ページ読み進めた。Kが下宿にやってきて、嫉妬心が湧き始めていくシーン。 |
2005年12月19日(月) |
イルクーツクかハバロフスクあたりの冷気を捕ってきて、まちがえて放してしまったような寒さ。ロシアの人たちなら毛皮の帽子をかぶって、赤くなった頬をゆるませながら、白い息はきはき楽しく会話するのだろうけど、東京人になりくだった僕は何かするにつけ寒い寒いばかり。それ以外の言葉を忘れてしまったようだ。 |
2005年12月18日(日) |
電車の中で漱石の「こころ」を読み返していて、主人公の父に死が忍び寄ってくる場面で、ふとこれが自分の父親の話だったらどうなのだろうと考えてしまい、その切実さのせいで文章が緊張感をもって自分に迫ってきた。 |
|
|
2005年12月17日(土) |
|
窓の向こうに澄んだ空の下、東京の街並みがどこまでも広がっていた。品川のホテルで結納。形式的なことは好きではないけれど、将来ふりかえったときに自分の中に残っているような一日になったように思う。フレンチ(特にスープ)が美味しく、シャンパンもワインも楽しめた。 |
|
2005年12月16日(金) |
お風呂からあがってオレンジジュースをぐっと飲みほして、ぼくのからだが吸収していく。 |
2005年12月15日(木) |
やらなければいけないことがどんどん広がってきて、それを効率化してこなしていく術を考えて・・・という毎日。 |
2005年12月14日(水) |
フレンチで忘年会。みんなが楽しんでくれたらからひとまず成功。係長が3月で退職されることになった。ひとつひとつの瞬間を楽しんで大事にしていきましょう。 |
2005年12月13日(火) |
冷気に覆われた一日。レポートの添付ファイルをシステムに提出できないという学生からの連絡があって、IEの設定等いろいろ試してもらって上手くいかず、とりあえずEメールでそのファイルを送ってください、と指示したら、しばらくして電話があって自己解決したから大丈夫とのこと。念のため、システム内から添付ファイルを覗いてみたら、健康関係の科目でここ二週間の朝昼晩に食べたものが事細かにファイル中に記してある。朝は毎日チーズにフルーツ、ヨーグルト。夜は必ず麦ご飯と納豆・・・。二十歳の女の人ってこんな健康食をとっているんだなってびっくり。・・・とそこまで見て、なぜ自己解決したかちょっと分かった気がしてみたり。 |
2005年12月12日(月) |
仕事で来年度に向けて大きな構想を考えているところ。授業をWEBで流して受講を希望する社会人からクレジットカードで受講料をとるという仕組み。オンラインすべてを対象にできるため、かなり効率的な収益モデルが描けそうだし、サービスの向上もはかれる。さらに他のところに先んじれる。それには収録を大量に効率よく行って、WEBに上げる仕組みも必要でそこに例の補助金を投入してはどうかなと考えている。 |
2005年12月11日(日) |
一日ストーブの前でのんびり読書。暮れてからコート着て図書館までお散歩。 |
2005年12月10日(土) |
|
渋谷でジョシュア・マーストン「そして、ひと粒のひかり」。痛烈に身体的な痛みを感じさせる映画だった。何ら危険もない現代の日本で生きている僕らにとって苦難とは多くは精神的なものであり、自分の身体を賭したものであることはほとんどない。コロンビアという国で生きていく主人公のマリアにとっては、苦難を乗り越えて生きていくために、敢えて身体を使うことが選択肢の中に簡単に浮上してくる。身体を賭けるという意味もわからぬままに、マリアは麻薬の運び人になる。人を人と見ないような冷たいやりとりの中で、マリアはようやく自分の生きる道を見つけることができる。結果的に彼女の未来は光明のあるものになったわけではあるけれど、決してその過程が正しい判断とはとても思えないし、安易だったとしかいいようがない。僕が感銘を受けたのは、死と隣り合わせのような身体的苦難をもってでも生き抜こうとする人たちがいることである。またそうした苦難を乗り越えて生きていけたときにこそ僕らは本当に生と死の意味がわかりえるのではないかということである。死など希薄で形もなく、痛みを受けることなく生きている僕を十二分に揺り動かす映画だった。南米や中南米の映画は生と死というものに真摯に向き合っている映画が多いし、実際にそういう生活なのかもしれない。いい映画をみたと思う。 |
|
2005年12月9日(金) |
忘年会に向う車の中で学長の隣に座って、私もここで働いて二年数ヶ月がたちました、って言ったら、「大きな顔しているからもっと昔からいるかと思った」とか言われて苦笑い。忘年会の終わりに「あと30年を支えるのは君たちです」とか言われて背中ばんと叩かれたのはいいけど、ここに30年もいるのかなと真に受けて逆に酔いが覚めてしまったよ。なんだか少しずつオトナになっていくわけだなぁ。ずっと清冽な小川の流れのようにいられたらいいな。 |
2005年12月8日(木) |
鶏の炊き込みご飯に最後に茗荷を入れたらいい感じ。+思いつき料理で卵をだし汁とお酒と醤油少々で溶いたものをごま油で軽く炒めたセリとあえて半熟にしてみた。お味噌汁もできたし、あとは・・・。 |
2005年12月7日(水) |
お風呂上り、電気ストーブに火照りながら、オスカーピーターソンのピアノを聴いているのです。 |
2005年12月6日(火) |
次から次へ仕事こなして夜。身のぷっくりした牡蠣ご飯つくって食べたら、もう眠る時間。 |
2005年12月5日(月) |
||
九州から帰ってきました。熊本では大学時代の先輩諸氏にも会えたし、友人(故人)のご家族ともたくさん話すことができてよかった。長崎では医者を目指して国家試験を間近に控えた先輩と夜飲みにいった。医者になることや子どもをもつことのよさをたくさん話した。ほんとうにいい先輩をもったことに感謝。それにしても長崎は寒くて凍えた。この冬の初雪を長崎で見るなんて思いもよらなかったよ。 |
||
 |
 |
 |
 |
 |
|
2005年12月2日(金) |
打ち合わせ資料をつくっておきながら、肝心の打ち合わせをする時間がなくなるくらい、やることが次々にあった。気づいたら夜とっぷりで再び星空の下を帰ってきたのでした。 |
2005年12月1日(木) |
今週は矢のように過ぎていく。後輩の力が伸びてきて、自分の手の届かなかった範囲の仕事をどんどんやってくれるからかなりありがたい。それでも来年度に向けて準備しなければならないものが多くて、やらなければならないことはいくらでも出てくる。夜、母親と一時間もの長電話。相変わらず話をしていると、突飛な方向に飛んでいって、ブラックボックスにもぐりこんで再び地上に出てくるといった展開。自分も間違いなくその影響を受けているのだと思うと不思議な気になってくる。正月は久しぶりに家族がそろうことになりそうで、母はずいぶんと張り切っているみたいだ。 |
2005年11月30日(水) |
今日は青空が澄んでいて美しかった。仕事に没頭していたら既に宇宙の闇の中に落ちていて星がかすかに瞬いていた。 |
2005年11月29日(火) |
大学時代の研究室の先生や後輩との飲み会。ぜんまいを巻き戻したかのように楽しかった。流れ星が瞬いてすれ違う、その瞬間に光を放つ、そういうことが人との出会いなんだって思った。もし自分が光を出せる相手ならばずっと大事にしなければいけないって思うよ。 |
2005年11月28日(月) |
お役人さんがやってくるので、そのための準備資料つくり。一つの資料作るのに朝から晩までかかってしまった。他の部署から内線がプルルときて「まだですか」の催促。今日は絞りに絞った雑巾状態ですよ。夜は夕食つくるのが面倒で、冷凍うどんをもどして鶏肉や青梗菜などと一緒に食べた。料理研究家?のケンタロウがNHKでうちにはいつも常備してます、って胸を張って言ってたからまぁよしとしよう。 |
2005年11月27日(日) |
駅前のイチョウが映える秋晴れ。渋谷まで「そして、ひと粒のひかり」を観ようと思ったら満席(さすが東京)で敗退。仕方なく、シネマライズでブルース・ウェバー「トゥルーへの手紙」を観てきた。反戦映画であったが、残念なことにひどく退屈な代物だった。どうもアメリカ人が共有できて、日本人にはわからない何かがそこには描かれていたように思う。アメリカ人にとって、アメリカとはこの映画で出てくるような自由で動物や家族との愛情に包まれている明快な世界なのだろう。それが911で貶められたことに対する恐怖からの脱却をテーマにしていたように思う。反戦映画はいいのだけど、結局この映画の見方は一面的で自分たちの世界を外から守るというところしか描かれていないように思う。だから、日本人たる僕が見ても何の感興も湧かないってことなんじゃないのかな。 |
2005年11月26日(土) |
珍しく一日家の中にこもっていた。クリスマスソング聴きながら読書などしてたよ。あとは、ポッドキャスティングとかvlogとかSNSとかそういう流行りもののネット記事など読んで唸ったり、大学時代のサークルの分厚い50周年誌を読んだり、ペンネアラビアータつくったりってとこかな。 |
2005年11月25日(金) |
イチョウの葉がキャンパスの小路に輝いているのだけど、僕はもうそれを手にとってもちかえったりしなくなったのだな、と気づいてみたり。 |
2005年11月24日(木) |
いろいろなことをやりたくて、やりきることもできなくて、いつも一日の幕は閉じる。 |
2005年11月23日(水) |
|
吉祥寺まで自転車で出かける。ダンディゾン寄ってオリーブのパンを、雑貨屋でスウェーデン製の布を(糸が少しほつれていたせいでずいぶんと安くなってた)、近くの酒屋で薀蓄の書いてあったスペインの白ワインを買って帰宅。夜はマカジキにハーブとパン粉をかけセロリ・クレソン・エリンギ・ピーマンなどと一緒にオリーブオイル使ってオーブンで焼いてみた。どんな魚かと思ってネットで調べたら、老人と海で出てきたような魚がヒットして老人以上に驚いた。いったいどこで捕ったのだろう。ダンディゾンのパンは相変わらず美味しい。 |
|
つい先日亡くなったビジネス書の大御所ともいうべきP・F・ドラッカーの「非営利組織の経営」も同時読み。仕事柄、読んでおいた方がいいとある人のブログで薦められていたものだ。アメリカの成人の二人に一人、総数にして9000万人の男女が非営利機関で無給で週に最低で3時間、平均で5時間働いているという冒頭の文書にまず驚く、というかむしろ「嘘でしょ」という疑義しか挟めない。アメリカ人はキリスト教が根底にあるからじゃないの?とSが教えてくれてなるほどとも思う。確かに資本主義自体が信心深いプロテスタントから生まれてきたものだものね。社会貢献というのは彼らの身体にしっかりと刻み込まれているものなのかもしれない。一方でなぜ日本人はそういう考えに至らないのか。仏教も関係しているのだろうし、教育や社会環境も違うのだろうとも思う。なかなか興味深いテーマかもしれない。 |
|
2005年11月22日(火) |
赤く燃えるヒーターの前でアルコールを飲める至福。 |
2005年11月21日(月) |
業務を委託している会社のミスが発覚。それに対応するのに午前中が消える。それから新設学部のe-learningの具体的なプランを練ったり、文字化けの報告などに対応したり・・・であっという間に夜。机にかじりついてるばかりで楽しいとは言えなかったかな。 |
2005年11月20日(日) |
|
ニューオータニ美術館でルーシー・リー展。美しい曲線と薄くシンプルな陶器がよかった。陶芸というのはとても幾何学的な世界なのかもしれない。これを数学にしたらきっと美しい数式が描けるのだと思う。器は果物を受け取るだけのものでなく、僕らの気持ちだって受け止めることができる。少なくとも彼女の器はたくさんの気持ちを受け止めてきたに違いない。 |
|
2005年11月19日(土) |
|
天気がよかったから自転車乗って吉祥寺まで。外に出ると、ジャケットだけじゃぴりりと寒い。井の頭公園周辺を散歩して、nigiro cafeでサンドイッチ食べて帰ってきた。帰りに近くの酒屋でワインを買い込んできた。能書きのあるものをわざわざ選んできた。この前読んだ本にはそういう人種のことをロハス系と分類していた。(まぁ否定はしない。)ワインのうち2本を自転車のかごに入れて、これから職場の先輩の新築祝い&鍋会に行くのです。 |
|
 |
 |
2005年11月17日(木) |
社会人のe-learningだとなかなか大学と一体感を感じることが少ない、と学生アンケートにあったから、現在ブログを画策中。12月のスクーリングで試しに使ってみようかと思っている。毎日の構内の様子を写真でUPしたりすると、大学に愛着をもってもらえるんじゃないかなって。 |
2005年11月16日(水) |
仕事は目の前のものをひとつひとつこなしている感じ。来年度のプランを練っていく仕事が多いかな。そうしてまた一日が過ぎて、朝夕の空気は研ぎ澄まされていく。 |
2005年11月15日(火) |
豚肉のブロックを買ってきて、大根とくつくつ煮てみた。大根は包丁を倒すように切って断面を凹凸にするのがコツらしい。夕食後は3日連続のケーキであった。 |
2005年11月14日(月) |
今夜はミートソースのパスタとキャロットポタージュとサラダをつくりました。キャロットポタージュは初めて作ったけれど、ジャガイモも一緒にミキサーでかけたら結構上品な感じに仕上がったよ。でもおあずけ状態なの。おなかすいたです。 |
2005年11月13日(日) |
近所のフレンチで彼女のBDを祝う。カルパッチョと黒豚肉のローストを食べた。赤ワインを一本開けたらふらふら。これで鬼門も克服かな。美味しいものを食べると幸せだね。 |
2005年11月12日(土) |
有楽町でヴィム・ヴェンダースの「ランド・オブ・プレンティ」。ヴェンダースらしい一作。全般的に何かが始まりそうで始まらないような単調なストーリー運びでそれでいて観た後に何かが残っていく感覚をもたせる。そして車からの風景の撮り方とシーンの挿入の絶妙さ。ベトナム戦争以降、脅迫観念にかられて、911で頭のねじが飛んでしまったかのうようなポール(ジョン・ディール)は、アメリカそのものを象徴するかのようだ。常に不安に苛まれ、人との信頼を築くことができない。すべてをモニターで監視し、自分のやることなすことを録音、録画する。自分は正義だと信じ、自分が誤ったことをやっていることに気づくことがなかなかできない。美しい姪のラナ(ミシェル・ウィリアムズ)はそうした叔父の変人的な言動を優しく包み込める存在。さらに異文化を小さいときから実体験で知ることによって、自己中心的な物の見方をする叔父を変えていく存在。この映画で被害者的な役回りになったのはパキスタン人であり、ずっと被害者意識の強いアメリカ人ではないというところもミソだろう。 |
2005年11月11日(金) |
イワシを買ってきて、薄力粉をまぶして、オリーブオイルで焼いてみた。最後にバルサミコ酢をかけて甘みをつけて、粉チーズをふりかけてみたら、いい感じ♪ もう少し、凝ったものもつくりたいなぁ。 |
2005年11月10日(木) |
空芯菜炒めをつくった。心が空というのは道教的というか深みのある名前で好きだし(実際には芯がないという意味なんだろうけど)、炒め物のシャキッとした歯ごたえもよい。空芯菜を初めて食べたのはシルクロードでの放浪行で中国を旅したとき。僕はこの炒め物にはまって(そして中国人は火を扱うのが上手いから、この炒め物を絶妙につくるのだ)、毎晩のようによく食べた。日本じゃ、ついぞ見かけなかった野菜だったのだが、とうとう最近スーパーに出回るようになってきて、初めて買って来たってわけだ。胡麻油で豚肉、ピーマン、生姜、ニンニクと炒めて、醤油とお酒、オイスターソースなんかで味付けした。歯ごたえもしっかり残って美味しくできた。塩味だけでもいけそうな感じもしたよ。そしてビールによくあうことこの上もなし。 |
2005年11月9日(水) |
お風呂あがりにハーパーを飲んでる水曜日の夜。もう少し、本を読む時間があるといいのだけど、なかなか。ネットを再開して思ったのは、結局ここは情報への欲求が増すところなんだなってこと。一度、ひとつの扉を開くと、そのあとの扉が次々に開いて、そこに情報がわんさかとある。それをパクパクマンのごとく、食べようとして、食べきれないという感覚。ネットやっていると相対的にテレビって見なくなってしまうね。21世紀はほんとにすごいところだなぁ。 |
2005年11月8日(火) |
内田さんのブログhttp://blog.tatsuru.com/archives/001341.phpや評論家中俣さんのブログhttp://d.hatena.ne.jp/solar/20051102に紹介されていた三浦展の「下流社会 新たな階層集団の出現」(光文社新書)を読む。マーケティングアナリストらしくデータのクラスタ化によって、現代の若者の特徴をあぶりだしていくところがなかなか面白い。下流といっても結局、自分らしさを大事にしていて、三種の神器を使いこなしているわけだから、それで一時的にでも幸せならたとえ搾取されるとしてもそれは危機というほどのものではないとも言う。だから、社会学者がデータ分析を単純に問題化していたり、行動が短絡的で無邪気に見えるところには手厳しい。ただし、マーケティングアナリストは職業柄、我田引水的な学者に輪をかけて、データを使っていかにもそうであるかのように見せるのが得意な人種でもありそうだから、眉唾的なところが多いような気もするけれど。(実際にはどの程度の有意水準があって、データがクラスタ化されているのかがよくわからないし、データ数が少ないという指摘には反論できなさそうだものね。)ちなみに概要については上の二人の感想を読めばわかると思う。それにしても中俣さんはきちんと自分の視座をもっていてすごいなと思うよ。 |
2005年11月7日(月) |
|
「世界の裏側が僕を呼び込んでくれた日に」
|
|
|
|
|
2005年11月6日(日) |
渋谷シネマライズでダニー・ボイル「ミリオンズ」。想像していたよりも楽しめる映画だった。イギリスらしさがよくでていたけど、フルモンティのような低所得労働者の時代はもう終わって、既に高級住宅街があって、poorな人を探すのに苦労するようなところがあって、まさに時代を反映しているように思えた。主人公の少年がpoorな人にお金を施そうとしてそれをわざわざモルモン教のアメリカ青年達に見いだすところは面白い。それでいてポンドからユーロへの変換期に焦点を当てていて、イギリスもヨーロッパであることをいよいよ認識しだしているのかもしれない。少年の為替感覚に父親が驚いて「本当に俺の子か?」というところが笑えて、近くに座っていてやたらと受けのいい(外人さんらしい)外人さんよりも早く笑った(ここだけちょっと勝ったと思った)。しかし、ダニー・ボイルは最初の「シャロウ・グレイブ」が一番面白いと思うけど、これいかに。 |
2005年11月5日(土) |
NTTの工事の方がやってきて、KDDIの設定も電話越しに変えてもらって、ようやくネット開通。長かったー。 |
2005年11月4日(金) |
吉祥寺で20〜30代前半の職員飲み会。開始20時半に慌てて行ったら浮かぬ顔をした幹事だけがいて、「全然集まらないですよ」。みんな忙しいみたい。結局、2時まで飲んだのでした。 |
2005年11月3日(木) |
三茶で白井晃演出「偶然の音楽」を観劇。オースターの原作にかなり忠実なストーリーの流れになっていて、椅子が並び、後半は方形の石の並ぶ舞台も簡素ではあったが、この物語にはよくあっていた。主演の仲村トオルは声が低くてよく響き適役。ジャック・ポッツィ役の小栗旬も、僕のイメージしていたポッツィ像(へらへらした感じのしけた男)とはまったく異なっていたものの、ジャニーズ系で軽い感じの演じ方が案外適役だったようにも思えた。この物語にはいくつかのテーマがある。ひとつは物事には流れがあり、それは他のものと調和することによって成り立っているということ(主人公はそれに逆らったために、石積みという調和の必要な作業に従事することになる)。ひとつは運命は自分で切り開いていくことができるように見えても実はそれは神の掌の中でのゲーム程度のものかもしれないということ(主人公は絶えず自分を掌中に収めている、姿の見えない支配者の存在に脅かされている)。ひとつは僕ら自身の存在を確認する作業はとても難しいということ(それは結局人とのつながりの中で生まれるもので、主人公はポッツィとの共同作業の中に自己の存在を見つけたように思うが、結局ポッツィーの消失した後には、彼自身の存在というものがひどく不確かになってしまう。) |
2005年11月2日(水) |
物を捨てることって過去を忘れ去るってことと同義なのかもしれないね。 |
2005年11月1日(火) |
システムにログインできない人がでてきて対処に頭悩ました。ネットが理由と対応方法を調べてシステム会社に相談して、夜の20時にシステムの設定を変更してどうにか事なきを得た。我ながらスピーディーで的確な対応だったと思うよ。 |
2005年10月31日(月) |
学長に呼ばれた会議でe-learningについての発表。こうしたことが初めての割には上々だったと思うよ。春に僕が作文して申請した文科省への補助金が通って、今後数年間一千数百万円がおりることになって、学長に「大変だね」と変な労い方だったけど声をかけてもらった。とにかく、これで僕は当面給与をもらう資格はあるってことだね。 |
2005年10月30日(日) |
ハロウィンということで、10月の初めの北海道行きで買ったカボチャでポタージュをつくる。サツマイモを少し入れたら、深みのあるよい味になったよ。ベランダのパセリを刻んで入れる。それに鶏肉のバルサミコ酢の照り焼き風、サラダ、ダンディゾンのパンに、金曜の余りの白ワインといった夕食。彼女と出会って一周年というわけだ。 |
2005年10月29日(土) |
スピッツなど聴いてるお休みの昼下がり。 |
2005年10月28日(金) |
月曜日の会議での発表用の資料作成を夜一挙にやる。ネットを駆使して、総務省やら文科省やら、他大学のセミナーの発表資料を集めておしまいっと。こういうことやってると、どんな情報であっても誰もが手に入れることができる時代であることを実感できるよ。 |
2005年10月27日(木) |
この前の京都のお礼のメールがけっこう届く。学生の満足度調査としてアンケートを集計中なのだけど、そちらでも好意的な意見が多い。そういうのを読むと、自分もいろいろな人のために役立てているんだなぁって単純に嬉しく思う。この仕事のいいところはそんなところ。 |
2005年10月25日(火) |
KDDIの案内によると今日からネットが繋がるということだったので意気揚々の接続の準備。・・・なのにつかない。どうもモデムの信号によると、回線のほうが繋がっていない模様。NTTかKDDIかこの部屋の配線のどれかがおかしい模様。テレビの見れない部屋の次はネットのできない部屋?ちょっとdisappointed。 |
2005年10月24日(月) |
夕刻、オフィスに残光が差し込んで部屋の中がオレンジ色になって、「世界の終わりみたいだなぁ」ってつぶやいたら、「世界の終わりってこんなに明るいの?」なんていう突っ込み。「明るく終わるって感じじゃない」なんて答えたら普通に笑われた。暗いエンディングってなんか想像できないな、今は。 |
2005年10月23日(日) |
近くの蕎麦屋で蕎麦焼酎と辛味大根の蕎麦をいただく。この店は駅前にオフィスがあったときに週1回は行ってたところで、JAZZがかかっていてくつろげる。たった一杯の焼酎で意外にも酔ってしまったのでした。 |
2005年10月22日(土) |
日帰り京都。手提げかばんで出かけて仕事も成功、アイーダのポスターにちょっとため息混じり終電近くの新幹線に飛び乗る。今年のロード戦はこれをもって終了。 |
2005年10月21日(金) |
フィンランドの現代デザインをNHKでとりあげていたので観てみた。アールトから最新のデザインまですべて自然との調和を考えた気持ちのいいデザインばかり。もっと気持ちよく生活することって多分できるのだと思ったよ。また、北欧に行きたいなぁ。 |
2005年10月20日(木) |
村上春樹の新しい短編集「東京奇譚集」。「偶然の旅人」と「ハナレイ・ベイ」を読んだところだけどいい感じ。思った以上というか、あまり期待せずに読み始めただけに(好きな作家だからあまりに期待してはずれるのが嫌だというのもあったかもしれない)、ちょっと驚きだった。うん、それにしても、面白いとはいいことだ。 |
2005年10月19日(水) |
物事は好転しているのか、空転しているのかわからないけれど、続いていく。キャラバンみたいにもっと愉快に暮らしていかなっきゃなぁ。 |
2005年10月18日(火) |
動物園のシロクマの檻の中みたいに淡々とした一日だったよ。 |
2005年10月17日(月) |
木曜の面談を受けて、仕事のやり方を若干変更。効率性よりもコミュニケーションを重視。これまで普通に頼んでいた仕事も自分でこなすようにして、さらに他の人の仕事をひとつひとつチェックして丁寧にサポートすることにした。おかげで残業時間が延びたって、・・・当たり前か。しばらく、こんな感じでいこうかな。 |
2005年10月16日(日) |
東京ステーションギャラリーで加守田章二展。20世紀後半の陶芸家。若い頃つくった花瓶からして既にセンスがよく驚かされる。色合いやラインなど現代的な感じがして日本をかけ離れた感じもするのだけど、素材そのものは日本的なものを踏襲していて、それらがうまく調和していた。<<自分の外に無限の宇宙を見るように、自分の中にも無限の宇宙があり>>、それを統一させていくことが彼の芸術だったようだ。見応えがあって、ほんとうによかった。 |
2005年10月13日(木) |
上司と上半期の成果について面談。求められているのが今以上みたいでちょっとたじろいじゃった。仕事があまり大変じゃなさそうなのが(実際、大変じゃないんだけど)、周りからは楽をしているように見えるとかそんなこと。だから大変になるとこまで挑戦ってことなのかな、ふむ。まぁ、その上をいきませう、いきませう。 |
2005年10月12日(水) |
サッカー日本VSウクライナ戦をTVで観る。さすが敵地ということで最後は審判にゲームを壊されてしまった感はあったけれど、力の均衡した良いゲームだった。中田はやはり欠くことのできないプレイヤーだと改めて認識。フィールド内の監督とも思えるほど、ここぞというところでチームに統制をつくるし、どんな状況でもボールをキープして感情的にならない。そして中村の正確なキック。ピンポイントで次々と前に当ててチャンスをつくるところは流石。以前はトリッキーなプレイばかりが目立っていた松井はフランスで成長したようで、前線でボールをキープし続け、そこから巧みに前に抜けていくような、相手が嫌がる選手になった。 |
2005年10月11日(火) |
金子勝、アンドリュー・デヴィット、藤原帰一、宮台真司の対談「不安の正体! メディア政治とイラク戦後の世界」を読んでいる。宮台真司は援助交際やオタク系の社会学者なんだと思っていたら、ここでは特にメディアにおける世界の仕組みについて力強く述べている。若干、人(ex.ネオコン的言動の福田氏など)をこきおろすところが感じられるけれど、意見は真っ当でもしかしたら勘違いしていたかもしれない。ここに絡んでくる国際政治学者の藤原氏の意見もなかなか面白い。藤原氏の言うアメリカでの選挙の方向性の変更が非常に日本と似ている。<<ニューディールから公民権運動の時代までの民主党の票の集め方は、基本的には政府の予算を分配して、それで支持を獲得するという、非常にわかりやすいものでした。これは具体的には政治利益を組織化して、組合や農民団体といったものがベースにあり、それが集票マシーンになっていた。>><<共和党のほうはメディア選挙なんですよ。メディアを操作してその場限りの争点を作り、それをテレビで流して相手に勝っていく。p.196>>
また、イラク戦争の原因については藤原氏はこう説明する。<<今回の戦争は、アメリカ資本と保守勢力が大団結して勃発したという見方はたぶん間違いだと思う。(略)むしろ少数のかなり突出した役人や政治家や企業が政権をハイジャックしたと捉えるべきでしょう>>また、911以降ネオコンが<<多様性を認めない文化は逝ってよし>>に<<カント的な合意の時代から、ホッブズ的な力の時代への移行>>を加えて、一時的に強大になっていることを宮台氏は指摘する。情報操作が強くなってきている時代にどのように国際政治や経済を見ていくのかがこの本の主眼と言えるだろう。本の帯には『もっとリアルな認識を!』『踊らされるな!』という文字が刻印されている。 |
2005年10月10日(月) |
アキ・カウリスマキ「白い花びら」。サイレント・ムービーであるが、心情に合わせたような音楽が印象的。田舎で幸せな暮らしをおくっていたにも関わらず、不意に訪れた不足感によって、女は知り合ったばかりの男と新しい希望をもって街へ出てしまうが、女の希望は程なくして絶望に変わっていく・・・というストーリー。妻をとられる男はこの映画では気の毒な存在として描かれているが、彼は妻自身を結局のところ知りえていなかったのであり、幸せであるということを日々の幸せの中で実感していても実はそれを共有できていなかったということに気づくのが遅かったわけである。そして最終的な決着のつけ方も、古典劇的に直截的過ぎて、そこで何かが救われることはない。白い花びらは二人の幸せ、あるいは女性の思いを暗喩している。 |
2005年10月9日(日) |
渋谷ライズで犬童一心「メゾン・ド・ヒミコ」。ゲイを演じるオダギリ・ジョーがかっこよく、それでいて存在感がある。「人に必要とされることこそが、生きていく上で何よりも大事であり、そうしたことが得られる場所を人は何よりも大事にするものなんだ」というのがテーマだったように思う。一方で柴咲コウ役の女性が感じる「自分のために他のものを捨てたのに捨てたものを好きだと言える心情への戸惑い」には完全に救いがなかったように思う。ただ、だからこそ、この映画には意味があるのかもしれない。金属のようなざらついた心象音ともいうべき音楽もよかった。 |
|
|
2005年10月8日(土) |
原美術館でやなぎみわ「無垢な老女と無慈悲な少女の信じられない物語」展。老女と若い女の対比がみごと。美醜と老若は常に僕らと一体にあって分かちがたい。どんなに美しく純真な女もやがて年老いて皺だらけの手をもつようになるだろう。そうしたものへの直視と残酷さと受け入れなくてはならない諦観を観るものに植えつけているように思う。老いているからこそ得られる美しさというものももちろんあるだろうがここではそこまでは触れてはいない。すべては永遠ではないことを悟ることも大切なこと。もうひとつガルシア・マルケスに触発されて創られた砂女の話も味わい深くてよかった。 |
2005年10月7日(金) |
連休に入るのに仕事が残ってしまってどうしようかなってところで飲みの誘い。コミュニケーションを優先してさっさとオフィス出る。恋破れた友達の話聞いてて、思わず飲みすぎて、帰り雨降る中、他の友達を巻き込んで自転車で転ぶ。 |
2005年10月6日(木) |
昼ごはん食べてるとき、後輩とこの前の札幌の夜の記憶試し。二人とも二次会と三次会の記憶が相当曖昧で大笑い。一次会から移動するとき階段で躓いて脛を打って痛かったのだけはなんか覚えてたり。 |
2005年10月5日(水) |
雨降りにスーツ少し濡らして、でも何かクールな気分してたり。軽快なジャズピアノ的雨音みたいな軽口放って曇り空だって蹴散らせ水曜日。 |
2005年10月4日(火) |
振替休日で、何か本でも読もうとして押入れにある本のぎっしり詰まったダンボールを探っていたら出てきたのが読みかけのナボコフの「ロリータ」。栞が全体の4/5のところにあったから一挙に読んでしまうことにする。限りなくアブノーマルに美的陶酔に酔いしれる主人公の独白はなかなか面白いのだけど、いかんせん話が長過ぎるような気もした。母国ロシアを出てヨーロッパを遍歴し、最後の最後で容易には懐柔できないアメリカに至ったナボコフの経歴を考えれば、伝統的なスタイルを保つヨーロッパ的要素(母親)を打算的にも捨て、粗野で悪趣味なものが入り混じりながらもその処女性と純粋性に甘美せざるえないアメリカ的要素(娘)への転換をストーリーにしたとも言えるような気がする。 |
2005年10月3日(月) |
若干身体が重いけど一定速度で仕事をこなす。出張のお礼状やらお礼メールを機械的に書いて、手当を機械的に計算してって感じで独創力はまったく関係なし。お昼は学生課の方(僕が入ったときの人事担当)と食事して、少子化や高齢者医療費、都市の防犯などについて留め止めもなく話す。高齢者向けに自給自足程度でもいいから畑を用意することで、医療費削減と食料自給率微上昇とコミュニティの結束づくりがはかれるんじゃないかって思いつきで話したら、妙に感心してた。 |
2005年10月2日(日) |
|||||
二週連続の札幌。今回は出張だったけど、非常にリラックスできた。一緒に連れていった後輩が「仕事とは思えなかった」なんて言ったくらい。 |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||